CLASS AA :スピーカードライブアンプは松下電器製品。
「初段増幅器出口端と次段増幅器出口端の最短ルートにはR1がある」図示である。
**************************************
su-a700の回路抜粋
上のモデル図とは結構形が違う。
1chあたり20個部品を使っている。 webで出回っているものとは部品数から異なるので、この回路で実験することをお勧めする。cは沢山いれてます。そのおかげで相は進みます。
ブリッジ回路はv-amp出力で焼損したようでワット数が変更になっている。
a700なので40wは出るアンプ部。
この図が示すように次段へは信号ラインが3本ある(1ch)。⑮、⑯は取り出し位置同じで 行先が違う。抵抗値に違いがあることが読み取れる。
信号強さは ⑬からの抵抗値と比率で決まる。 最終はspラインに辿りつくようだ。何だろうね?
vーampと呼ばれているのは 超古典なpish pull回路(1970年頃のまま)。current damperが入っているので1971年だとは思う。
動作は、class bからabの動作。conduction angleは180度、200度?程度なので、class aではない。
push pullをclass Aと呼ぶ知的水準だと、「バイアス」について全く学習していないことがバレてしまう。
**********************************************************
MOSクラスAA(自称)の回路を搭載したテクニクス の音響機器. スピーカードライブアンプはSVI3201シリーズのどれかが搭載されている。
16V 22uFの方向からみて 出力(無信号時)はDCマイナス側らしいことも読み取れる。お得意のブリッジ回路???はこれから眺めてみる。
松下電器の音響ブランドがテクニクス。
Technics1 で検索。
ハイブリッドICは松下(実態は三洋電機にて製造)。
落ちていたがメーカー品らしい。 電流アンプは、B class.(ppなので B class表現は正しい)
回路図が落ちている機器として
1, レシーバー SA-GX230
2, SU-A700
3, SU-A900
4, SU-900S
向山一人氏が興した「興亜工業」(現 KOA ) のCHIP抵抗 と 自社(松下)のCHIPコンデンサが載っている。
向山氏は 国会議員を3期つとめた。「 伊那谷にはライバルなし」だったのをオイラは覚えている。
0402 chipを世界最初に売り出したのは松下。 2000年秋のこと。業界では速報がでたほどの衝撃だった。(オイラは速報を受けた側)
このアルミ線で0.6A流せるらしい。
IGBTでは同じランドから複複数のアルミ線がでている(富士電機のIGBT siteに写真ある)
CLASS AAと謳ってはないが、そんな回路が落ちている。
LRの信号が「signal level det」(Q551 )の前回路で混ざる設計にはなっておる。R553.R554は3.9Kなので 確実に混ざる。落ち着いて眺めるが、 一見ALCのような動作?????。
ブリッジ回路でのRは低ワット品。1/4wを1/2wに変更した履歴あり図面も落ちていた。ブリッジ回路で、貴重な音エネルギーを食っている証が公開されている。全量の何%を食っているかも知りたい。
「WEB時代に突入して散見されるCLASS AA ブリッジ回路ワット数」 とはワット表示が違うので、 現行解釈が正しくない可能性もそこには存在する。
ClassAA回路を内蔵したse-A100
technics_se-a100_sm.pdfをダウンロード
ここにブリッジ回路があるはず。
******************************************************
松下電器2000年代の某事業部長(工業新聞に顔写真よく出ていた)とは顔見知りであったが、都会に行ったままで 狸と狐の出る田舎には戻ってこなかった。
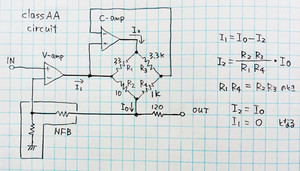
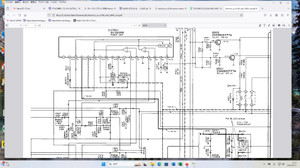
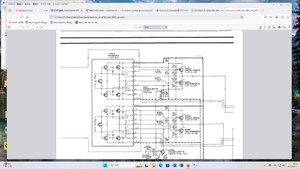

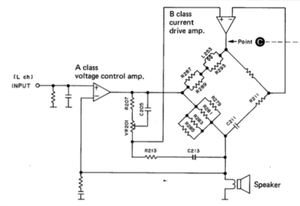


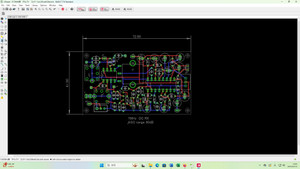


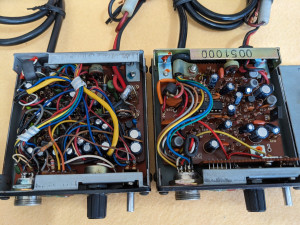
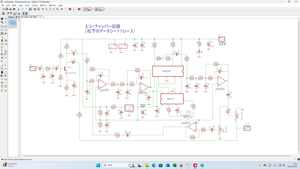

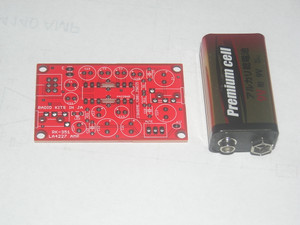
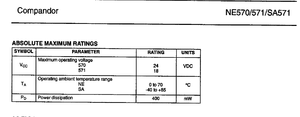
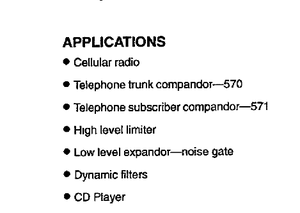

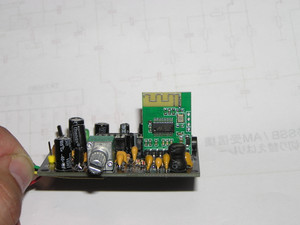






最近のコメント