2球式 レフレックスラジオ 自作 (6EW6+6EW6) その5
2球でスピーカーを鳴らそう作戦です。
YAHOOにて、トランスを調達しました。
「1:3」との事でしたが、テスターでΩを測ると1:9位です。(270Ω:2500Ω)
昇圧比は高い方が助かります。
1次側のヘンリー値も少ない方が,「低域ブーストから逃げれる方向」に働きますね。
100Hチョークが3.54KΩ。
「トランス10KΩ:8Ω」が340Ωなので、現用のトランス(チョーク)よりは
ヘンリー値が小さそうなのが、推測できます。
↑購入したトランス。
右が購入のまま。左のように、天側に端子を振り直しました。
NHK第一を受信中。SP端でのバルボル読みは0.1V位。
現行のチョーク(トランス10KΩ:8Ω)⇒「1:3」トランスに換装して14dbほどup。
音量面では充分です。(3S-STDより大きな音出せます)
受信中、「1:3」トランスの2次側をバルボルで見ていると、ピークで0.7Vまでは振れてました。
AF段のバイアスは-1.5V~2Vが良さそうです。(レフ部のゲインを下げるのが正しい??)
リップル音は、依然として付いてきます。
AVRの後に、RCの平滑をもう1段追加しました。もうスペースが苦しいです。
3wayのSPで鳴らす音には、遠いです。
手持ちの10cmSPで聞きます。(高域も低域も音圧が取れないSPが、ベターです)
ここまで実験してきましたが、
**********************************
検波後は、トランス負荷でAFに引き渡すのが、一番効率がよいですね。
(圧倒的にグッドです。)
トランス負荷(チョーク負荷)ですと、電源のリップルにとても敏感なので
平滑回路はCR2段程度ではダメですね。リップルを引き込むイメージに近いです。
(3S-STDは,いま4段にしてあります)
AVRも高音の広域ノイズを有するので、
何か工夫がないとノイズに埋もれた信号を聞くことになります。
(2011/NOV/5追記
秋月から購入したSPで聴くと、シャー音も減るので、リップルの高調波のようです。)
**********************************
この2球レフレックスでは、よい実験をさせてもらいました。
追記2011/Oct/17th
造れば判りますが、補助アンテナは不要です。
見てくれが悪いので、自分の机の上で鳴らしてます。
2011/NOV/07 追記
SSGから1Khz変調の入力↓
SSGから400Hz変調の入力↓
これだけ、低域が持ち上がってます。
雑誌には、このような特性情報が載っていないのが、大変不思議です。
レフ部のプレートから見て、インダクター負荷はLPFを形成していますね。
(盛り上がり方がキツイです)
去年初めて作った再生式ラジオ(チョーク負荷)でも、
聴感上、低域が持ち上がっていたので、「変だなあ」とは想ってました。
こうやって波形で確認しつつ、
回路図を眺めると、LPFになっているのが理解できました。
*****************************
追記 2012/Feb/26
アイドル状態(無信号状態)↑の初段バイアス電圧。
同調時。↑0.05Vくらいの変化。
シャープカット球って、こういう挙動の球だと想っています。
*****************************
追記 2012/Mar/3
AF段のトランス負荷(インダクター負荷)は、
負荷そのものの固有共振周波数に左右され,
ハイブースト 或は ローブーストになることが判りました。
並列共振時は、ハイインピーダンスに成るためですね。
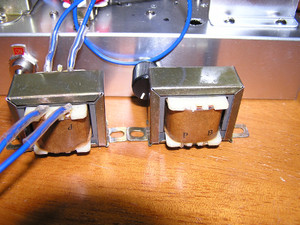

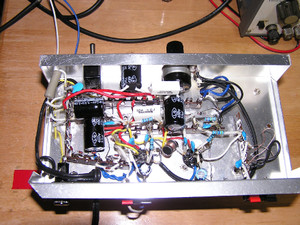
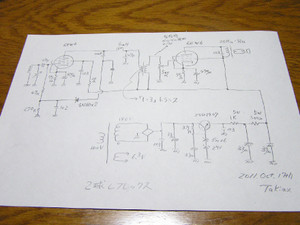
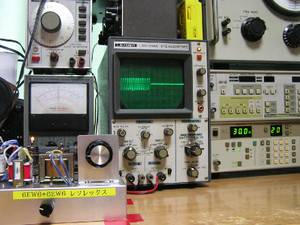



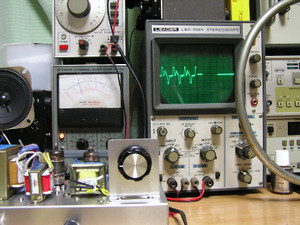

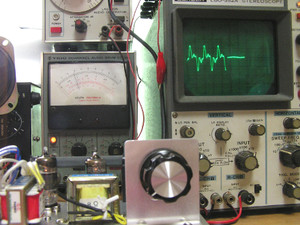

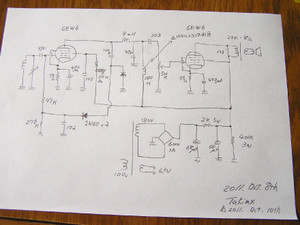
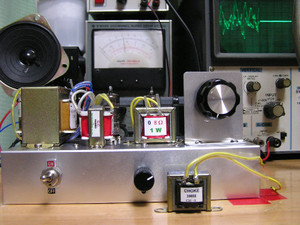



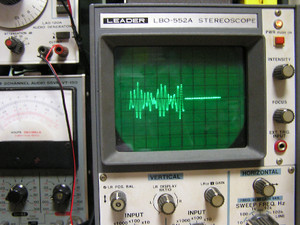
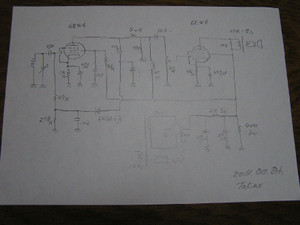


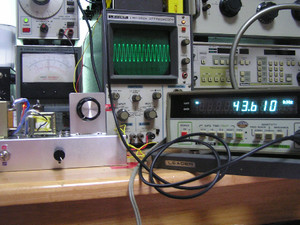

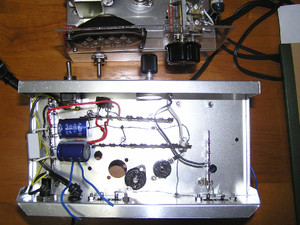

最近のコメント