csb455を発振させて使う。
今日はこの続き。
フォトカプラーでAM変調を掛ける実験の続です。
前回は455kHzに届かないので、部品配置を少しかえた。
2sc1906で試すと1/3の150kHz帯でのoscになった。
2sc181blでこの周波数。
« 2024年11月 | メイン | 2025年1月 »
今日はこの続き。
フォトカプラーでAM変調を掛ける実験の続です。
前回は455kHzに届かないので、部品配置を少しかえた。
2sc1906で試すと1/3の150kHz帯でのoscになった。
2sc181blでこの周波数。
回路はここに公開済み。
455kHzマーカー基板を7例。
・「IFT調整専用ツール」はテストオシレーターではないのだが、「455khz テスト オシレーター」との謎用語が近年独り歩きしている。さて発振者(発信者)はだれだ?
・発振強度の強弱ができて、発振周波数の可変をできるものをテストオシレーターと名称づけされ、それで商標登録されていた記憶だ。テストオシレーターを名乗るならば、その二つができてからになる。
すでに領布中の455kHz IFT調整用マーカー基板は下記①、②、③、⑤、⑥、⑦の6種類。(TA7310はスキル必要なので領布しない)
①オールトランジスタ式。RK-07(サイズ42 x77mm)
上級者向けの基板。初心者は遠慮ください。
泉 弘志先生が公開したトランスレス変調を2SCにしてみました。
これは ここに紹介ずみ。 基板は領布中.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
②NE612式。RK-30(サイズ 42x 60mm)
ダブルバランスドミクサー(NE612)を使った455kcマーカー。 ここに紹介ずみ。
綺麗な変調になります。初心者向け基板。
このne612マーカーキットはyahooにあります。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
③TA7320式(サイズ 42 x52mm)
三種類目として、かなり小型のIFT調整基板を興してみた。 OSC内蔵DBMとして東芝TA7320にしてみた。国産DBMのマーカーです。FINALを2SC2061等にすればオール国産半導体になる。
中級者向けの基板。初心者は遠慮ください。
上記①、②の455khzマーカー同様に電波飛ばして調整する。ラジオに結線してもよいが電波で飛ばす方が調整は楽だろうと。
・レゾネータに村田製CSB455を使うと 「68PF+トリマー20PF」でほどよく455.0kHzに調整できる。
①
OSC波形。
②
③
トーンはこの位の周波数。
④
AM変調波形.
⑤
電波でとばして確認。黄色いアンテナ電線をバーアンテナに近づけて測定。
⑥
大きさはこの位。
TA7320で455kHzマーカーをつくってみた。
通算324作目。基板ナンバー RK-72
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
④TA7310式
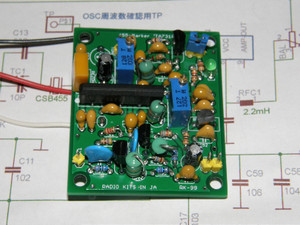
上級者向けの基板。初心者は遠慮ください。
記事はここ。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
⑤シグナルインジェクター兼用
YouTube: signal injector for diy tube radio
RK-164
**************************************************************
⑥オールトランジスタ式。RK-230
RK-07のtone部をtwin-t回路にしてみた。上級者向けの基板。初心者は遠慮ください。
「レゾネーターが同じ型番で、同じ回路でも発振周波数が1kcほど低い」ので、磁場?が違ってきているぽい。
**************************************************************
⑦ フォトカプラーでAM変調かけたシグナルインジェクター。RK-337
音楽を聴くには不向きです。ne555は矩形波出力なのでフォトカプラーで遊んでみました。実験用の基板。RK-337
乗算が必須なssb復調(アナログ復調)。これを理解できなきゃ、無線は止めた方がよい。
パルス振幅復調も勉強してね。
搬送波が存在するamとdsbは同期検波で復調。
検波デバイスに、ca3028,ne612.sn16913を使った基板。
ne612は455kHzではマイナスゲインになるので、お薦めはしない。設計センターが45MHzなので、1MHzより低い周波数ではロスる。
超古典(mc1496以前)に開発されたca3028はゲイン取れる。455kHzではca3028を推奨。
mc1376は455kHzでゲインが取れそうなので、プロダクト検波させてみる。
**************************************************
同期検波の方法 : 「乗算回路を使う」のはプロダクト検波とおなじ。
① プロダクト検波回路と違う点は、
乗算デバイスへの注入信号に「受信した電波信号をリミッター通過(RFネライ=0.4V~0.7V、逆相)させて」それを入れる。
感度?(変換効率?)は注入量の強さと比例関係にあるので、調整は「強い注入量を絞る方向で合わ」せる。
② リミッターデバイスにはTA7061が使い易い。
RFスピーチプロセッサーは、ハムジャーナルでは1975年発行の2号が古い記事だ。
もともとTXの追加オプションとして米国で人気なったのを、八重洲FL-101(1974年発売)に搭載したのが国産機の起点になる。
ケンプロKP-60は、欧州ノミの市で出回っていた手書き図面がベースになっている。が使われおる。
RFスピーチプロセッサーの実験中。
「NE612+455kHz IFT」なので、AM波形はこの程度。ne612では1MHz以下は不得意。
20mV/devなので120mV位。
DSBを止めて AMのままリミッテイングさせた。
復調後のオペアンプ回路がボコボコと発振中。後段オペアンプを止めて復調レベルを100ミリボルト位にあげるのがよい気配。
当社は、1961年(昭和36年)12月に設立。水晶デバイスおよび応用製品のメーカーとして、水晶振動子や水晶発振器、その他水晶フィルタ機器を扱い、コンピューターやスマートフォン、カーエレクトロニクス、医療機器など幅広い用途で用いられていた。近年では防災無線や無線基地局向けの需要が伸び、大手産業機器メーカーを主体に3割程度を海外向けに販売。
2023年9月期の年売上高も約58億4100万円を計上。
ケンプロのKP-12A、アイコム等では、このNKD製のSSB フィルター。
ラジオ少年の電源トランスは、手頃なサイズで使いやすい。
単球ラジオで常用している型番BT-0Vは、2024年2月に売り切れ。
5球ラジオでFITする型番 BT-1Vも品切れ。
YouTube: 6AW8 single radio : reflex + regenerative :2023/Aug/24th
***************************************************************
YouTube: one tube radio D.I.Y 6BR8. 2024/Dec/1st
トランジスタラジオ用のIFT,OSCも枯渇モード中。
文字入りダイアルは日本市場にない。 中国では製造していない。
***********************************************************
12AU8は国内では枯渇中。
6KE8は 運よくゲットできた。
低周波信号でOSCをON/OFFさせるとAM変調になる。
フォトカプラーでoscをon/off させてみた。
YouTube: radio maker tested. using tlp559.
osc波形。今回の配置では、455kHzに届かない。ZTB455,CRB455,CSB455みな455に届かない。
マーカーには使えそうだ。
oscが強すぎるらしい。 rezonatorの発振回路は弱くすると発振停止になるので、塩梅が難しい。
音楽を聴くには不向きです。ne555は矩形波出力なのでフォトカプラーで遊んでみました。実験用の基板。RK-337
ギルバートセル型dbmとしては、最古のmc1496が発売されたのが1969年。ギルバートセルは1968年に論文公開ではあるが、その原型となるのは数年前から他者によって公開されている。
ギルバートが欧州に戻って手掛けたdbm SL1641は高性能でもある。
過去に公開済みであるが、dbmとしてMC1496、AN612、NE612、AN610、SL1641、TA37310、TA7320、SN16913、CA3028、S042P等でAM 変調させてきた。
今日はne612と似たことができる モトローラ のMC1376pで「osc+変調」させた。 波形はam変調。
有線電話の子機用(FM通信:いわゆるtelecom )として開発されたのがMC1376。
NE612は国際電話通信網の第二局発用に開発されたIC. このNE612では455kHz帯動作は、20dBほどもマイナスゲインになるのが特徴。
YouTube: testing balanced mixer 'mc1376p' for amplitude modulation
動作上限は20MHzくらい。波形はta7320よりgood.
am ワイヤレスマイクとして使える水準。9v動作だとoscが強すぎるので、6v位で使うのがコツ。
過入力時の波形はバーストになった。 方向性を掴んだので、基板手配した。
等価回路を視るとCが入っており、FM変調したい雰囲気が視れる。実際には内部Cでは全然不足で外部バリキャップのチカラでFM変調している。(FM用に基板化したがAMモードのままなので、AM用に基板をこれから換える)
OSC強さは図中47PFと270PFに依存する。下記図ではFM変調は掛からない。(製造時より内部Cが減少しており、周波数を振れない)
MC1376実験基板は続く。
1.5W 出力のTDA8942P.
初回リリースは1999年。 datasheet ver2が2020なので、1999年4月14日にver1公開。
。
この92万の男は、道徳の概念がないので、育ちが違うらしいことは判った。
簡単に裏切ることも推測されるので、友達は少ないだろう。
「オペアンプでスピーカーをならしちゃった。50mWもでた」の作例(2024年8月)。VR maxだと五月蝿いので8部ほどで鳴らしている。
YouTube: NE5532 amp can drive speakers like this. max50mW
OP2134並みの低ノイズ。 LM386で遊ぶよりも実用的な回路。 ここにて公開.
「ne5532の4パラアンプ」の続として、ne5534で基板化してみた。
YouTube: ne5534 stereo amp : d.i.y
半固定をグルグル回しても波形変化がよく判らないので、合わせには歪率計がmust らしい。
通算586作目。 RK-334にてリリース。
NE5532 シングルを6Vで鳴らすと50mW超えで出力される。ここに公開済み。
YouTube: NE5532 amp can drive speakers like this. max50mW
NE5532 の4個使ってみた。4パラなのでノイズは1/2になる。
YouTube: QUATORO NE5532 audio amp :6V
150mW程度はでてくる。 ICの相性があるの 非反転入力ピン間での電位差が大きいとガサガサノイズになる。 つまり、ガサノイズに為らない組み合わせを探し出す。
通算572作目。 RK-322
BGMとしては、ne5532 シングルで6畳間で足りる。
セラミックパケージ品(1977~1980年代)は 世間で云うように音は良い。 これは事実。
このセラミック 5532は、1983年の製品らしい。SE5532A.
ICでの音を決める要素として、
1、 リードフレームの材質。
無酸素銅がベースらしいがフレームシートメーカーごとに成分が異なる。音色が違う。
松下製BBDでは、セカンドメーカー品の音色が劣る理由はここ。
2, シリコンウエハー上でのパターン幅、引き回し。
これは非公開情報になるが、 引き回しでノイズ強さは増減する世界。
3、洗浄具合。純水の純度。
最近のコメント