DFKさんのweb shopはすでにclosedしています。(2015年にclosedだった記憶)
中国産部材に比べて高価だとメールにて攻撃されたので closedしています。至って普通価格でリリースされていたのですが、製造コストを理解できない方からの大攻撃だったようです。
中国産の超再生式トランジスタキットは2011年~2017年では市場に出てないですけどね。
大手企業を中心に「技術力=タダ」と捉える風潮が日本に根付いているので、エンジニアは使い捨てにされています。 その現場を多数見てきましたし、それをオイラも経験もしています。
超再生のプロト基板を興しましたので、興味のある方はお寄りください。
********************************
先日、真空管式FMチューナー も治したので、
FMつながりで トランジスタ式のチューナーキットにTRYです。
オイラが知る限り、FM帯のチューナーキットはこの会社しか現行販売していないです。
①スーパー式モノラルチューナーキット DBR-601
②超再生式チューナーキット DBR-402
上の2キットとも入手してみました。(ベーシックシリーズ> ラジオ系)
「有るようで無いのが超再生式キット」なので、
面白いキットをリリースされており、オイラは感謝しています。
DFKさんに承諾いただきましたので、UP致します。
ラジオ工作は、奥が深いのでただ半田鏝を握るだけの方には不向きだと想います。
実装のノウハウは体得するしかない世界ですので、 ラジオを自作で100台つくる頃になんとなく会得しはじめるものです。真空管ラジオを70台ほど造りましたが、まだ駆け出しの範疇だと想います。
web情報だけを眺めて、ラジオ工作にTRYする意志のない方は、そのskillのままで今後も
傍観者でお願いします。(ラジオパーツの値上がりが衰えるのを望みます)
★いままで、各種キット取説内容のUPを致したことはありませんし、
今後もそのつもりはありません。
回路等の著作権は製造販社に属しますので、その旨 皆々様ご理解くださいませ。
AMラジオ造りを卒業された方は、FM帯にTRYしてみてください。
★昔、フォアーランド電子さんが、27Mhz帯のトランシーバキットを学校教材として
販売されていたのを覚えておいでの方も多いと思います。
オークッションでも往時のトランシーバーキットが稀に出されていますね。
**********************************
超再生式チューナーキット DBR-402です。
オイラの財布にも優しい価格になっています。
チューナーなので、AF部は自前で揃える必要があります。
DBシリーズから揃えてもOKですし、自前で穴明き基板で組んでもOKです。
超再生の解説はweb上に多々上がっているので、そちらに譲る。

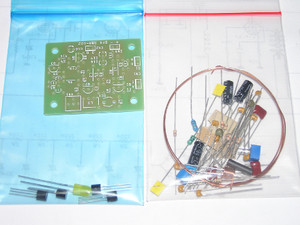
上の写真のように、部品点数が少ないので
ささっと組み立てられそうです。
半田は「昔ながらの半田」を薦めます。
鉛フリータイプは半田性が劣るので、できれば昔の半田を使ってください。
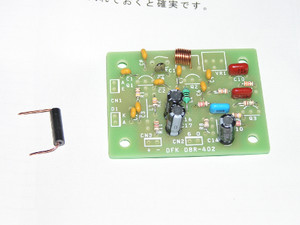
★回路を理解するためには、
信号が流れる順に部品を取り付けていくのがgoodです。
★半導体は熱に弱いので、後回しにします。
★回路L1は、脚を少し磨いて皮膜を剥がしてから、基板に載せた方が楽だと思います。
(線材がやや太いので、熱で皮膜が融ける前に銅パターンが負けそう)

他バンド用の部品も入ってました。
このキットを50MhzのAMに使うと面白そうですね。
一昨年? 50Mhzの超再生式3石トランジスタキット基板(完成品)がyahooで
そこそこの数売られてましたけど、手に入れた方は 今も使っておられます?
★バリコンを使って可変Freqにするので、 自前でVRやバリコンを揃えます。

もともとのトリマー位置にもピンを立てておきます。

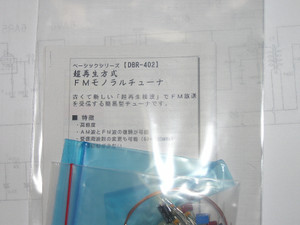
ワンワンの床屋に行った帰り道、綿半ホームセンターに寄ってみたら
丁度良い大きさの樹脂ケースがあった。即、購入した。
戻ってきてからケースに入れてみた。LEDはいつもの緑色にしてみた。

LEDのグランド側はVRのグランド側と半田付け。
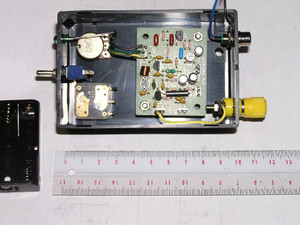
バリコンはFM専用のもの。VRはBカーブの50KΩ。
続きます。
TOP PAGE

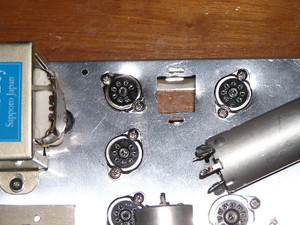

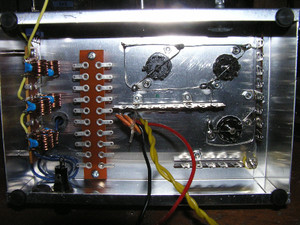

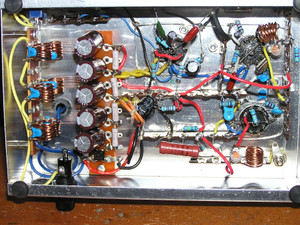

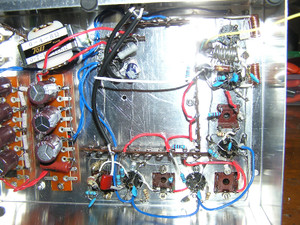


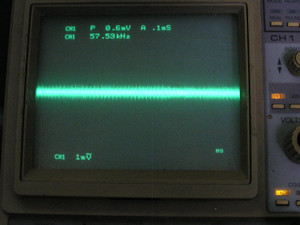
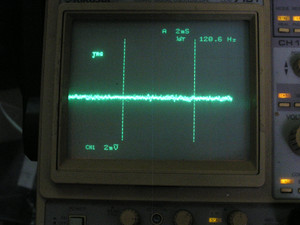
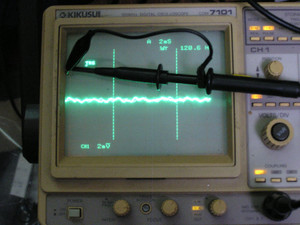
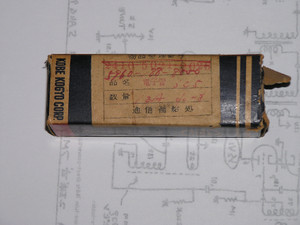






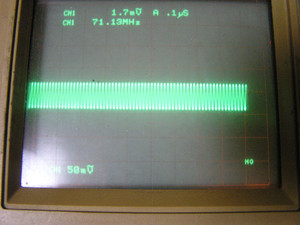
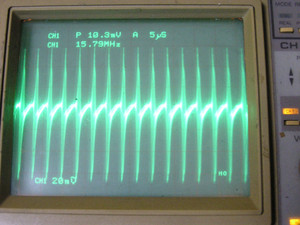
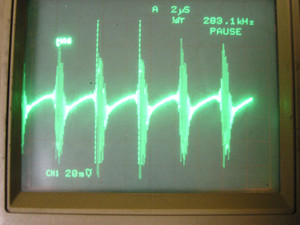
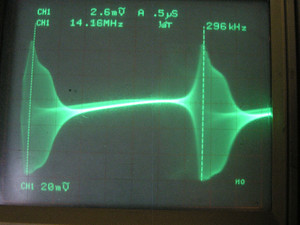
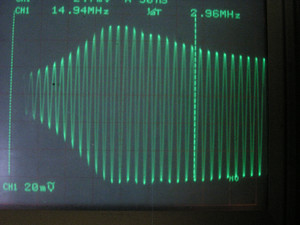
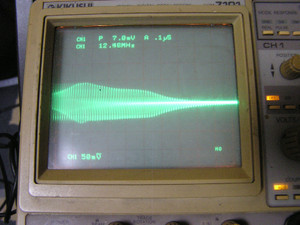
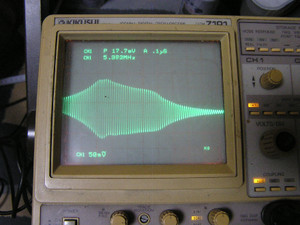
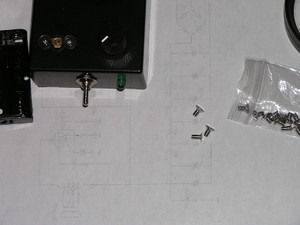












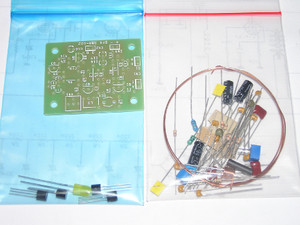
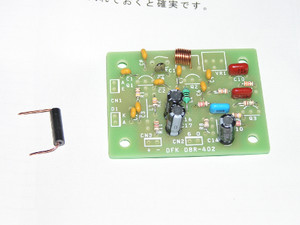



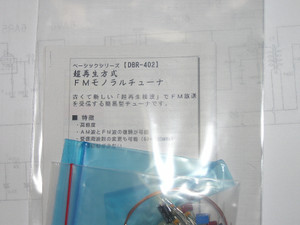

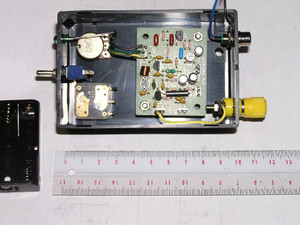








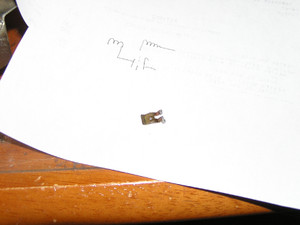



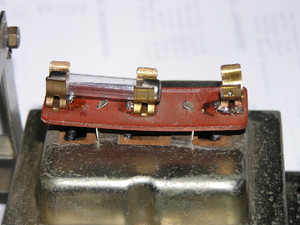

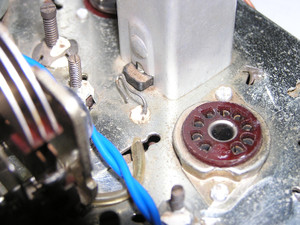





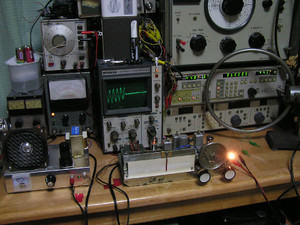
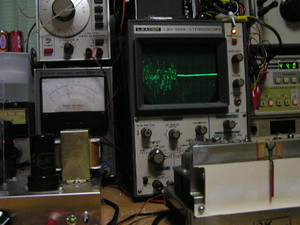


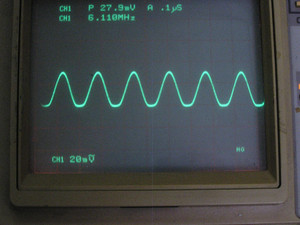
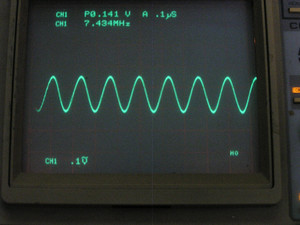
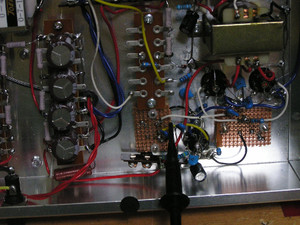
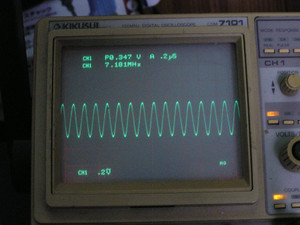
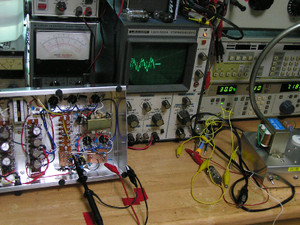











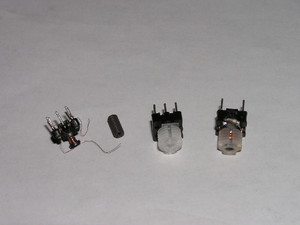
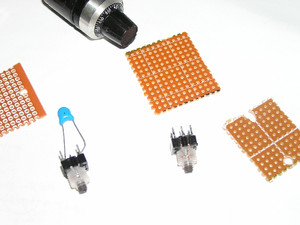
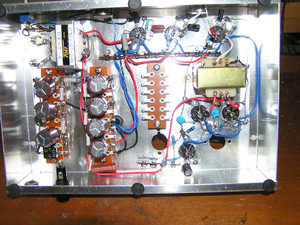




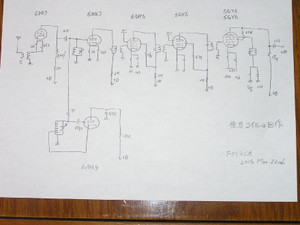

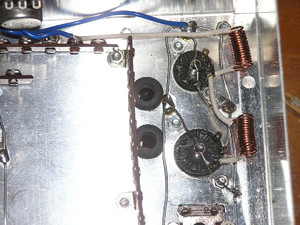




最近のコメント